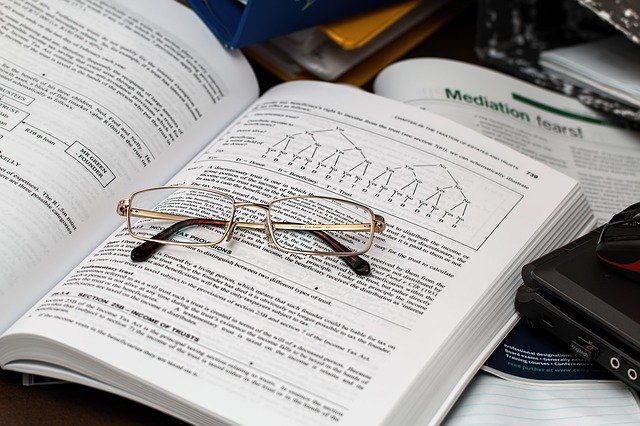物件の種類にかかわらず、建物の欠陥を素人が、購入前に見つけることはとても難しいですよね。
万一、購入後に欠陥を見つけても諦めないで下さい。法律や制度を知っていると、あたなを守ってくれますよ。
瑕疵担保責任

瑕疵とは、欠陥のことです。建物に何らかの欠陥が生じると、その場所にとっては、生命にかかわる重大事故を引き起こす可能性もあります。
そこで、民法や宅地建物取引業法で、この欠陥について細かく定められています。これが瑕疵担保責任です。
よく、業者さんのアフターサービスと混同している人も多いようですが、瑕疵担保責任とアフターサービスはまったく異なります。
| 瑕疵担保責任 | アフターサービス | |
| 責任 | 法律により、売主が負う義務 | 売主が買主との約定により負う義務 |
| 責任の対象 | 売買契約時の目的別にある瑕疵 | 約定期間内に発生した瑕疵・欠陥 |
| 瑕疵の種類 | 隠れた瑕疵に限定 | 約定に定めた範囲すべて |
| 責任期間 | 特約がない限り、民法に従う | 部位別に1年から10年の範囲で定める |
こうした瑕疵担保の責任期間について、法律ではどのように定められているのでしょうか。
民法
契約の解除または、損害賠償の請求は、買主が「隠れた瑕疵」の事実を知った日から1年以内にする。売主は、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしても、知っていて告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
宅建業法
不動産業者が売主の場合、その目的物の瑕疵担保責任の期間について、引き渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法で定めるものより、買主に不利な内容の特約をすることはできない。
住宅品質確保促進法
新築住宅の場合、売主は引き渡しの日から10年間、住宅の「基礎構造部分」について、瑕疵担保責任を負うことを義務付ける。
消費者契約法
事業者が売主の場合、その目的物に隠れたる瑕疵があるとき、その瑕疵により消費者に与えた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効となる。
住宅の品質確保と促進等に関する法律

売主が、新築住宅の基礎構造部分(基礎、土台、床、柱、壁、斜め材、小屋組、横架材、屋根および雨水の侵入を防止する部分)を対象に、瑕疵担保責任を負うものです。
| 保証期間 | 完成引き渡しから10年 |
| 請求内容 | 修補請求 賠償請求 契約解除(売買契約で、かつ修補不能な場合に限る) |
中古住宅の保証制度

中古住宅の保証制度は、既存住宅保証制度といい、新築時に、公的機関による中間検査または建築基準法による中間検査が実施された一戸建て住宅が対象で、売買契約による所有権移転前に、(財)住宅保証機構による現場検査に合格した住宅を、(財)住宅保証機構が一定期間保証する制度です。
保証期間内に、補修を伴うような事故が発生した場合、(財)住宅保証機構から、費用の一部が支払われます。検査に合格すると、住宅登録基準適合確認書が発行されます。
| 申請者 | 売主または媒介業者 |
| 申請時期 | 売買による引き渡し前 |
| 保証期間 | 構造耐力上主要な部分ー5年間 雨水の侵入を防止する部分ー原則2年間 |
| 保障内容 | 補修費必要な費用から10万円を差し引いた額の95% ※不動産業者が売主の場合は80% |
| 免責部分の負担 | 瑕疵担保責任の期間内は売主、その後は買主の負担 |
住宅性能表示制度

この制度は、「住宅の品質確保と促進等に関する法律」に基づき、客観的に住宅の性能を表示する制度です。
住宅品質確保促進法による、建物10年保証と混同されがちですが、この制度は任意なので、売主がこの制度を利用するとは限りません。
あくまでも、住宅の性能を評価する制度で、保証をするものではありません。なかには、この制度を利用するにあたって、検査費用を買主の負担としている新築住宅もありますので、事前に確認しておきましょう。
新築住宅の場合の性能評価制度
①設計住宅性能評価:設計図書の段階の評価をしたもの
②建設住宅性能評価:施工段階と完成段階の検査を受け、評価したもの
メリット
- 国が指定する第三者機関による評価なので、客観性がある。
- トラブルの際、国が定めた指定住宅紛争処理機関を1万円で利用できる。
中古住宅の場合の性能評価制度
①現況検査:外壁や屋根を部分ごとに検査し、評価したもの
②個別性能表示:構造、火災、空気環境など9項目について詳しく調べ、性能を個別評価したもの
メリット
- 新築を除く、すべての建物に適用可能。
- 国が指定する第三者機関による評価なので、客観性がある。
- トラブルの際、国が定めた指定紛争処理機関を1万円で利用できる。
- (財)住宅保証機構の「既存住宅保証制度」を条件付きで利用する資格がとれる。
土壌汚染対策法

大規模な工場跡地などに、マンションを建設する場合など、以前その場所にあった工場が使っていた薬品などによって、土壌が汚染されている場合があります。
そのままマンションを建設し、住民が暮らすと、健康被害が発生する恐れがあります。
そこで、こうした汚染された土地に、住宅を建設する際には、土壌汚染に対し、何らかの対策をしなさいという趣旨で作られた法律です。
不動産売買においては、重要事項説明書のなかで、土壌汚染についての報告がなされますが、土壌汚染対策法に基づく汚染指定区域の内外によって、その内容は異なります。
・売買の対象となる不動産が汚染指定区域内の場合
指定区域として指定されている場合、汚染の除去等の措置の要否とその内容を明記します。
・売買の対象となる不動産が汚染指定区域外の場合
土壌汚染対策法の指定はされませんが、土壌汚染の恐れがある場合、現地の状況や過去にあった建物の状況を明記します。