暗号資産(仮想通貨)で利益がある場合、税金が課税されますが、どの時点で利益が確定するのかを理解していない人が多いようです。
理解しないまま取引していると、多額の税金が課税されてしまう恐れがあります。
暗号資産(仮想通貨)で得た利益の確定時期、利益の計算方法などを詳しく解説したいと思います。
暗号資産(仮想通貨)の利益とみなされる取引

国税庁の見解では、「暗号資産(仮想通貨)の売却」と「暗号資産(仮想通貨)の使用」が利益とみなされる取引になるそうです。
では、売却や使用とは、どの時点なんでしょうか。
暗号資産(仮想通貨)のを日本円に換金したとき
→暗号資産(仮想通貨)の取得価格から、換金時の日本円のレートで換算した差額が利益とみなされる
暗号資産(仮想通貨)で資産を購入したとき
→暗号資産(仮想通貨)の取得価格から、資産を購入した際の暗号資産(仮想通貨)の日本円のレートで換算した価格が、利益とみなされる
別の暗号資産(仮想通貨)とトレードしたとき
→そのトレードによって増加した暗号資産(仮想通貨)の増加分が利益とみなされる
マイニングしたとき
→マイニングにより取得した暗号資産(仮想通貨)の時価が利益とみなされる
このように、暗号資産(仮想通貨)を売却または使用に該当するタイミングには、さまざまなものがあります。保有している暗号資産(仮想通貨)が、何らかの形に変わるような取引をした場合、注意しましょう。
暗号資産(仮想通貨)の計算方法
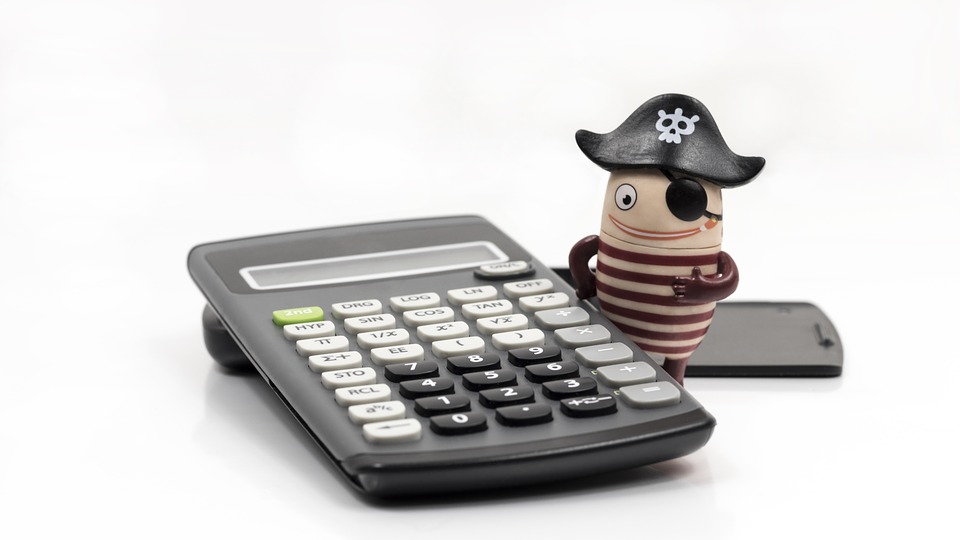
売却した金額-購入した金額=利益
単純な取引であれば計算は簡単ですが、実際の取引では、途中で暗号資産(仮想通貨)を買い増ししたり、保有している暗号資産(仮想通貨)の一部を売却することも多いと思います。
そのような場合の計算方法として、移動平均法と総平均法という2種類の計算方法があります。
移動平均法
移動平均法とは、暗号資産(仮想通貨)の取得価格(購入単価)を求める計算方法の1つで、複数の取引をした場合において、その暗号資産の購入の度に、取得価格を計算する方法です。
暗号資産(仮想通貨)を購入するたびに取得価格を計算するため、取引回数が増えるほど、計算が複雑になります。
移動平均法のメリット
移動平均法のメリットは、実際の取引の利益や損失額と近い数字を計算することが可能です。
また、相場の下落前に大量に暗号資産(仮想通貨)を購入し、下落後にそれらを売却した場合には、総平均法に比べて、利益が小さくなることがあります。
他にも、暗号資産(仮想通貨)を購入するたびに計算するため、納税額の予測が立てやすく、納税資金の準備をすることができます。
移動平均法のデメリット
移動平均法のデメリットは、何と言っても計算が複雑なことです。暗号資産(仮想通貨)の取引回数にもよりますが、取引回数が多ければ多いほど、計算が複雑で手間もかかります。
また、相場が上昇する前に暗号資産(仮想通貨)を大量に購入した場合などは、総平均法に比べて利益が大きくなってしまうこともあります。
総平均法
総平均法は、複数の取引をした場合でも、1年間に購入した暗号資産(仮想通貨)の平均単価で計算する方法です。
具体的には、年間の暗号資産(仮想通貨)の購入金額の合計額を、年間の暗号資産(仮想通貨)の購入数量で除して、取得金額を求めます。
総平均法のメリット
総平均法のメリットは、計算が簡単なことです。1年間に何回取引をしても、すべての合計金額で計算することができるので、移動平均法と比較して、計算が簡単になります。
相場が上昇する前に、暗号資産(仮想通貨)を大量購入した場合などには、移動平均法に比べて利益が小さくなることがあります。
総平均法のデメリット
総平均法は、計算が簡単である一方、実際の取引における利益や損失額と、計算上の金額が大きく乖離してしまう場合があります。
また、暗号資産(仮想通貨)購入時の平均単価で計算することから、相場の下落前に大量に暗号資産(仮想通貨)を購入し、下落後にそれらを売却した場合には、利益が大きくなってしまうことがあります。
他にも、1年間の合計金額で計算することによって、年末にならないと利益や損失の計算ができないので、納税額の予測が立てにくいというデメリットもあります。
どっちの計算方法がお得なの?
移動平均法と総平均法の2種類の計算方法をご紹介しましたが、どちらを選択したらいいのでしょうか。
どちらの計算方法を利用するかによって、その年の利益の金額は変わることがありますが、その差は、利益を計算するための対象期間を区切っているだけで、暗号資産(仮想通貨)取引を始めてから取引をやめるまでの利益や損失の総合計(生涯成績)は、どちらを選択しても、金額は一致します。
暗号資産(仮想通貨)同士の損益通算は可能?

暗号資産(仮想通貨)取引による所得は、雑所得に分類されます。
雑所得の中には、総合課税の対象になるものと、分離課税の対象になるものがあり、それぞれの利益と損失を相殺させることはできません。
暗号資産(仮想通貨)取引に関しては、現物取引と証拠金取引の違い、暗号資産(仮想通貨)の種類の違い、取引所の違いによらず、すべてが総合課税の対象となります。
そのため、違う通貨同士の利益と損失を相殺することは可能です。
暗号資産(仮想通貨)利益の節税ポイント

暗号資産(仮想通貨)取引の節税対策として、最も基本的な方法は、必要経費をしっかりと計上することです。どのようなものが、経費として認められるのでしょうか。
- 暗号資産(仮想通貨)の取得費
- 取引手数料
- 暗号資産(仮想通貨)セミナーの受講費・交通費・宿泊費
- 暗号資産(仮想通貨)に関する書籍や新聞など
- インターネット接続費などの通信費
ただし、通信費や取引用のパソコンなどで、暗号資産(仮想通貨)取引専用でないものは、全額ではなく、暗号資産(仮想通貨)取引に利用した割合を経費として計上します。
また、10万円以上のものは、減価償却資産となり、全額を一括で経費とすることができず、定められた耐用年数に応じて、少しずつ経費として計算します。
年間取引の計算方法

暗号資産(仮想通貨)取引の利益を計算するためには、取引所からダウンロードした取引履歴から、エクセルなどを使って集計する方法が一般的でした。しかし、この作業はとても大変で、多くの時間を要します。
そこで国税庁は、暗号資産(仮想通貨)交換業者に、年間取引報告書の作成を義務づけ、暗号資産(仮想通貨)の計算書を公開しました。
これにより、一部の計算は簡単になりましたが、この計算書では対応できないケースもあります。
そのような場合に役立つのが、損益計算アプリ【クリプタクト】![]() です。クリプタクトは、税理士も使っている安心で便利な損益計算サービスです。
です。クリプタクトは、税理士も使っている安心で便利な損益計算サービスです。
損益計算には、取引履歴をアップロードするだけで、最短10秒で暗号資産(仮想通貨)の損益計算ができる「クリプタクト」がおすすめです。



