これから不動産投資を始める人、また、新たな物件の購入に際して、オーナー自身が身につけておくべき基礎知識をまとめてみました。
失敗を未然に防ぐためにも、基本的な知識を身につけておきましょう。
物件情報の収集方法
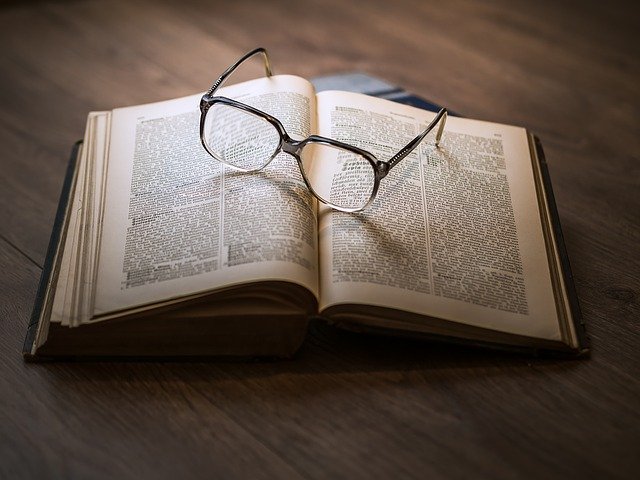
長期にわたる不動産投資においては、事前の情報収集が重要な意味を持ちます。
どんなニーズがあるのか、地盤の強さ、地域の将来性などの情報をある程度は把握しておかないと、物件選びや収支計画の失敗につながってしまいます。
特に物件は、立地や建物タイプ、入居者の属性などによって1軒1軒異なるため、入念な情報収集が必要です。
情報収集の方法は、新聞の折り込みチラシやインターネット、住宅情報誌など、多岐にわたり、それぞれ活用の方法が違いますが、現在、主流となっているのはインターネットです。
不動産投資専門のサイトは、不動産会社が運営しているものと、仲介業者が運営を行うポータルサイトの2種類があります。
どちらも、物件種別やエリア、物件価格、利回りなどから検索できますが、掲載された情報だけに頼らず、気になる物件を取り扱っている不動産会社に問い合わせをしてみましょう。
その際に注意したいのが、「釣り物件」です。これは、不動産会社が成約済みの「優良物件」を掲載して客を呼び込み、買い手がつかないような物件を売り込むという手法です。
釣り物件を見極めるのは難しいですが、実際に自ら現場に足を運ぶことをおすすめします。
物件のタイプと特徴

ひとことで不動産といっていも、投資物件の種類はさまざまです。
- マンションの1棟買い
- アパートの1棟買い
- ワンルームマンションの1室買い
- 一戸建ての1戸買い
1棟買いは、まとまった資金が必要ですし、長期的な計画が欠かせませんので、はじめはプロのアドバイスを受けることをおすすめします。
一般的に、1棟買いは、ワンルームマンションと比較すると、空室リスクを下げられるというメリットがあります。
ワンルームマンションの1室を購入した場合、空室になってしまうと、家賃収入はゼロです。
ローンを組んで購入した場合には、手持ち資金から毎月返済分を捻出しなければなりません。さらに修繕費や管理費などもかかります。
1棟買いでも空室リスクはありますが、建物の全室を持っていることで、多少の空室が出たとしても、残りの部屋の家賃収入で、ある程度カバーすることができます。
また、1棟買いの場合は、リフォームや修繕を自分の都合で行うことができますので、収益性アップのための手立てを幅広く施すことが可能なのです。
一方、ワンルームマンションへの投資は、相対的に少額から始めることができ、比較的売却しやすいというメリットがあります。
ただし、購入手続きなどの労力は1棟買いとほぼ同じで、融資を受けて購入した場合には、信用毀損を起こして、次の融資を受けられなくなる可能性もあります。
ネット利回りと表面利回り

物件を選ぶ際の重要ポイントが「利回り」です。利回りには「表面利回り」と「実質利回り」の2種類があります。表面利回りとは、収益を大まかに捉えるための指標です。
実質利回りとは、税金や管理費などのコストを差し引いて算出される、収益の指標です。
マンション広告などでよく記載されているのは、表面利回りです。しかし、賃貸物件を所有すると、さまざまなコストがかかります。
これらを換算せずに、表面利回りだけで資金計画を立ててしまうと、資金不足に陥ってしまう可能性があります。
また、広告の中で「満室稼働利回り」というのを見ることがあるかと思います。これは、空室を考慮せず、常に入居者がいることを前提として算出された利回りなので、あくまで参考にしかなりません。
賃貸物件を購入するのであれば、最低限、利回り計算ができるようにしておきましょう。
| 利益 | 特徴 | 利用 | |
| 表面利回り | 収入の額 (粗利益) |
簡単に算出できるが、表面上の収益しか把握できない | 投資の初期段階で検討するもの。主に広告などに掲載されている |
| 実質利回り | 収入から支出を除いた額(純利益) | 表面利回りよりも正確な収益性が把握できる | 具体的に物件を購入する際に検討する |
賃貸契約における権利と義務

オーナーは、入居者が居住に適した状態に物件を維持・管理する義務があります。物件の状態や設備が不十分である場合には、オーナーに修繕義務が発生します。
そして、オーナーが物件の保存に必要な行為を行う際、入居者はその行為を拒否することができません。
一方、入居者には賃料の支払い義務や賃借物に対しての保管義務、契約終了後に原状回復したうえで、オーナーに返還しなければならない義務などがあります。
このように、オーナーは法律によって物件の維持・管理が義務づけられており、入居者には物件を使用するにあたって、原状回復に努めなければならない義務が課せられています。
投資効果の分析方法

不動産投資を行う上で、所有している物件の投資効果の分析は欠かせません。現状の把握と将来予測は、投資の成否を決めます。さまざまな指標があるので、物件の状況を把握するための参考にしてください。
NOI(営業純利益)
これは、営業純利益のことで、賃貸経営を行う場合、毎月手元に残る収入を意味します。
家賃収入ー(管理費+修繕費+各種税金+共用光熱費+保険料など)で算出します。
CCR(自己資金利回り)
自己資金に対して、どの程度のリターンを得ているかを表します。経費などを差し引いた収入から、ローンで支払っている年間総返済額を引いた額がキャッシュフローで、このキャッシュフローを自己資金で割ることで算出します。
キャッシュフロー÷自己資金×100
PBM(資金回収法)
PBMは、投資の回収期間法という意味で、資金回収までの期間を計算し、ガイドラインに沿っていれば投資を続け、沿っていなければ投資をやめる判断をするための評価方法です。CCRとは反対に、自己資金をキャッシュフローで割ることで算出できます。
自己資金÷キャッシュフロー
K%(ローン定数)
K%とは、ローン定数のことで、銀行にとっての利回りです。融資を受けた場合、ネット利回り(FCR)が、ローン定数を上回っている必要があります。年間の総返済額をローン借入額で割ることで算出できます。
年間返済額(ADS)÷現在のローン残高
不動産投資に関わる業者

不動産投資では、不動産にまつわるさまざまな専門業者との付き合いが不可欠となりますので、代表的な業種をご紹介します。
デベロッパー
多くの場合、数十~数百単位の個数の大型マンションを開発する業者。土地の購入から建築、販売までを手掛けますが、販売は子会社や提携している仲介業者に委託するケースがほとんどです。
不動産仲介会社
戸建てからマンション、アパート、土地など新築・中古を問わず、不動産を紹介する会社です。多くの場合、賃貸と売買、それぞれを専門に行うところが多いのが特徴です。
なかには、入居者の審査から、不動産の管理まで行う会社もあります。
不動産管理会社
オーナーが所有している物件の管理を行うのが、不動産管理会社です。大きく分けると、一括借り上げと管理代行の2種類があります。
一括借り上げは、物件のメンテナンスや、入居者のトラブル対応などすべてを請け負う形態で、管理代行は、オーナーが管理業務を選択して、個別に委託することが可能です。
物件の管理を行い、価値を向上させる業務は、プロパティマネジメントと呼ばれ、収益性を高める意味でも、オーナーにとっては重要な役割を担っています。
不動産コンサルタント
不動産の専門家です。収益性のない更地の有効活用や、相続税対策など、オーナーの要望に沿って、投資計画の見直しやアドバイスを受けられます。
保証と保険

賃貸経営では、家賃滞納や自然災害による物件の修繕など、さまざまなトラブルがありますが、オーナーの負担を軽減できる保証制度があります。
家賃滞納・空室
すべての入居者が、毎月必ず家賃を払ってくれるとは限りません。なかには、家賃を滞納する入居者もいます。その場合でも、家賃収入を得られるのが「家賃保証制度」です。
保証内容は、会社によっても異なりますが、3~4カ月の家賃滞納が発生すると、家賃収入の70~100%を保証してくれるところが多いようです。
なかには、滞納者の明け渡し請求による訴訟費用や、弁護士費用を補償してくれるところもあります。
同様に、一定期間空室が続くと、家賃を保証してくれる制度もありますので、契約時に確認してみましょう。
火災・地震
突発的な自然災害に対して、事前に策を講じなければ、オーナーが莫大な費用を負担しなければなりません。一般的に、火災保険は、地震や津波、噴火などの自然災害による損失は補償の対象外です。
そのため、地震保険を火災保険に付帯して契約します。契約金額は、火災保険の30~50%、補償限度額は、建物が5000万円、家財が1000万円です。
入居者の死亡
何らかの事情で、入居者が亡くなられた場合、次の入居者が決まるまでは、数カ月の期間を要することになります。その間の家賃収入はありませんし、リフォームしたり、遺留品の整理をしたり、想定外の出費が相次ぎます。
独居老人で、相続人もいないとなると、オーナーの持ち出しになる可能性もあるのです。そうした損害に対して、費用を補償してくれる保険もあります。敷金を超える原状回復費用や、次の入居者が決まるまでの家賃収入を保証してくれる特殊な保険です。


